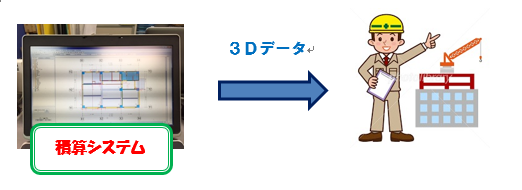さて、BIMの中心となると設計というイメージがあると思います。当然、設計では3次元データを作ることによるたくさんのメリットがあります。また他部門へのデータ連動の上流となる設計部門はBIMの主役ということが言えるでしょう。 しかし、ゼネコンでの3次元データの活用となるとどうでしょう。設計施工の割合が多いゼネコンでは設計部門が3次元データを作成し、積算、設備、施工などへ受け渡しすることで活用できますが、請負が中心のゼネコンでは設計からの3次元データを入手することは難しく、 データの受け渡しは図面か、あっても2次元のCADデータぐらいかと思います。
最近のBIMの活用として、施工部門での利用が注目されています。設計施工の割合が多いゼネコンでは設計で作った3次元データを積算や設備にデータを連動させて有効活用を図ろうとしていますが、 その中で施工部門へ3次元データを連動させ活用しようという動きが出始めています。施工部門への3次元データの活用では次の何点かが考えられます。
- 施工図への展開
- 施工計画(仮設、搬入、建方など)3次元データの活用
- 協力業者との3次元での打ち合わせ
- 近隣、役所などへの3次元データでの説明
- 3次元データからの躯体数量の算出
このようなこれまで図面やExcelなどでやっていた作業を、3次元BIMソフトを活用することにより、工期短縮やコストの削減、ミスの軽減に効果を出している事例が出ています。 日本建設業連合会(日建連)も一昨年、施工BIMの手引書(「施工BIMのスタイル-施工段階における元請と専門工事会社の連携手引き-2014」)を発行し、施工BIMのあり方を提唱しています。 このように施工部門でのBIM活用の有効性は大いに期待できますが、施工部門でBIMを活用するには、元になる3次元データを作成する必要があり、これには結構な労力必要です。 設計施工の物件であれば設計で作った3次元データを施工BIMソフトに連動させれば労力は少なくて済みますが、請負物件の場合でデータが手に入らない場合は施工部門で、 BIMデータを作成しなくてはならず、大変な労力が必要となります。
一般に日本のゼネコンは設計施工の案件は少なく、請負の割合が多いゼネコンが多いと思います。そういった会社で施工部門が3次元データの作成をすることはなかなか大変なことかと思われます。 別に今は困ってないから、今まで通りでいいやということもありますが、大手を中心にやり始めている施工BIMが、本当に現場にとって有効であると実証されれば、 施工BIMを活用しているところ、そうでないところでは生産性や品質の面で差ができ、ますます技術の差が広がる恐れがあります。では、施工BIMを活用したいと場合において、設計からの3次元データが無いような場合で、労力のかかる3次元データの作成で何かいい方法は無いのでしょうか。 その方法として考えられるのが積算部門での3次元データの活用です。
ゼネコンでは、請負物件の場合でも積算は行われます。現在のコンピュータでの積算システムは部材を1つ1つ拾う手法から、建物の形、すなわち3次元データを入力して拾いだすという方法が主流になっています(特に躯体積算)。 積算では数量を忠実に算出するため、柱、梁、床、壁などの躯体の断面情報、配置情報また段差、増打ちなどを図面に記載してある建物の形を正確に入力します。 これがすなわち施工部門に引き渡す3次元データの元となることができます(ヘリオスでは躯体の3次元データの作成だけでなく、間仕切り壁など仕上げの3次元データの作成も行えます)。 この積算で作成した3次元データを前回でお話ししたBIM共通フォーマットのIFCで出力し施工BIMソフトで取り込むことにより、施工部門での3次元データの作成の手間が大いに省力化することができます。
正直、設計施工の割合の少ないゼネコンにとって、BIMといってもその有効性を享受することは無く、あまりピンとこない感じがするとは思いますが、 将来、施工BIMの有効性が認められ、現場での3次元データの必要性が出てきたときには、いかに3次元データを早く作るかということが課題になってくるのではないかと思います。 その時には、積算データからのデータ連動が大きな鍵を握ることになるかもしれません。またゼネコンでは積算を外注しているところも多いので、積算を専業としている積算事務所にも3次元の積算データが要求されることも今後出てくるかもしれません。